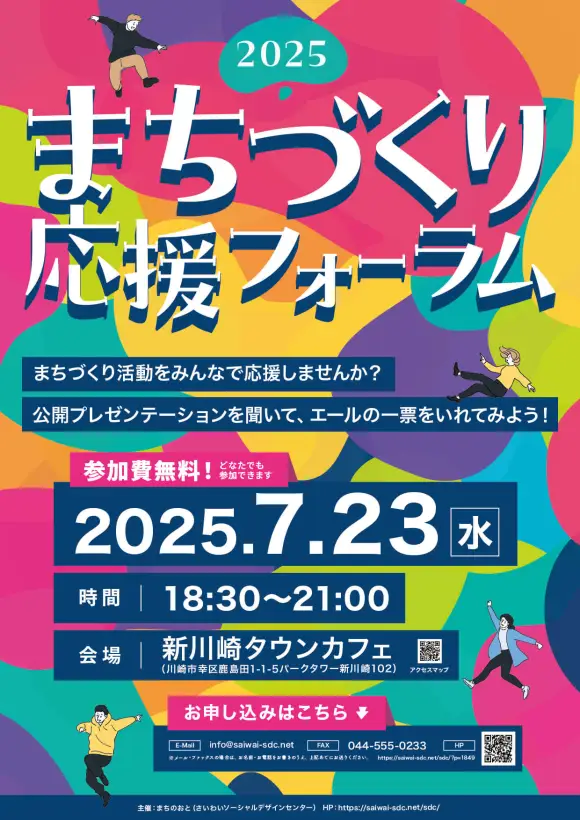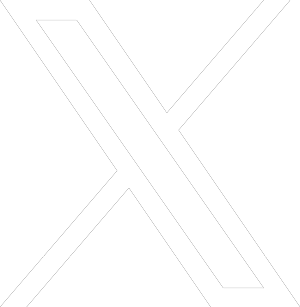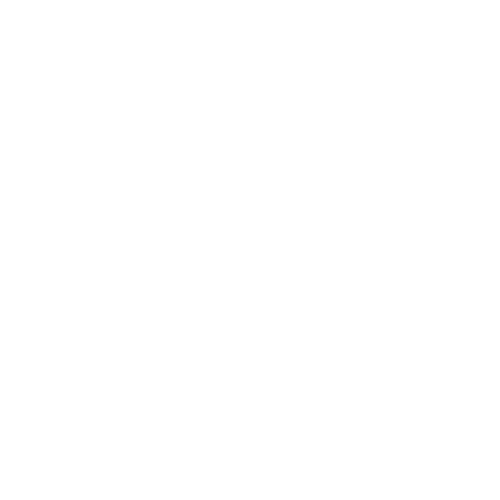シセンレッサーパンダ

丸い大きな頭に三角の大きな耳。
シマシマのしっぽはフサフサ。竹の葉っぱが大好物なんだ。
Contents
レッサーパンダってどんな動物?
レッサーパンダは、ヒマラヤ山脈の東側や中国の南西部にある高い山の森に住んでいる動物です。ふわふわの赤茶色の毛に包まれています。ジャイアントパンダと名前が似ていますが、実は全く違う仲間の動物なんですよ。レッサーパンダは、レッサーパンダ科という独自のグループに属していて、この仲間は世界中でレッサーパンダだけなんです。
体の特徴
見た目
レッサーパンダ(学名:Ailurus fulgens styani)の体は赤茶色のふわふわした毛でおおわれています。お腹と足は黒くて、顔には白い模様があります。長いしっぽには茶色と白のしま模様があって、このしっぽはバランスをとるときに使うだけでなく、寒いときには体に巻きつけて毛布のように使うこともあります。
特別な体のつくり
レッサーパンダには「第6の指」と呼ばれる特別な部分があります。これは手首の骨が変化してできたもので、親指のように使うことができます。この指があるおかげで、竹をしっかりつかんで食べることができるんです。ジャイアントパンダも同じような指を持っています。
レッサーパンダは木登りがとても上手です。するどいツメを持っていて、頭を下にして木を降りることができます。このような動き方ができる動物は、世界でもあまりいません。
どこに住んでいるの?
生息地
レッサーパンダは、ネパール、インド、ブータン、中国、ミャンマーといった国の山の中に住んでいます。標高の高い場所にある、竹がたくさん生えている涼しい森が、レッサーパンダにとって一番住みやすい場所です。暑さは苦手で、寒い場所の方が好きなんです。
食べ物
レッサーパンダは肉食動物のグループに分類されていますが、実際に食べているものの約95パーセントは竹です。タケノコや竹の葉を主に食べています。竹以外には、果物、木の根、鳥の卵なども食べます。時には虫や小さな動物を食べることもあります。
竹は栄養があまりないので、レッサーパンダは1日の大半を休んで過ごします。こうすることで、少ないエネルギーでも生きていけるようにしているんです。
生活のしかた
レッサーパンダは基本的に1匹で生活します。朝早い時間と夕方に活発に動いて、昼間は木の上で休んでいることが多いです。木の上で生活することが多くて、木登りや木の枝を渡ることがとても得意なんですよ。
レッサーパンダは絶滅の危機にある
現在の状況
レッサーパンダは、IUCN(国際自然保護連合)という世界的な組織によって、絶滅危惧種に指定されています。野生に住んでいるレッサーパンダの数は、とても少なくなっていて、今も減り続けています。
なぜ数が減っているの?
どうしてレッサーパンダの数が減ってしまったのでしょうか。大きな理由が3つあるんです。
1つ目は、住む場所がなくなっていることです。人間が森を切って畑や道路を作るため、レッサーパンダが住める森が減っています。森が小さく分かれてしまうと、レッサーパンダ同士が出会えなくなって、子孫を残すことが難しくなります。
2つ目は、密猟です。レッサーパンダの美しい毛皮を目当てに、違法に捕まえる人がいます。ペットとして売るために捕まえられることもあります。
3つ目は、気候変動です。地球の気温が変わることで、レッサーパンダが住みやすい環境が変化しています。竹が育つ場所も変わってきているため、食べ物を見つけることが難しくなっています。
レッサーパンダの分類
レッサーパンダは、レッサーパンダ科という独自の科に属する唯一の動物です。昔は、アライグマの仲間やクマの仲間だと考えられていたこともありましたが、最近の遺伝子の研究で、レッサーパンダは独自の進化をたどってきたことがわかりました。
遺伝子的には、アライグマやイタチ、スカンクなどが含まれるグループに近いことがわかっています。ジャイアントパンダとは名前が似ていますが、実はあまり近い親戚ではありません。ジャイアントパンダはクマの仲間なんですよ。
参照・出典元
- IUCN (International Union for Conservation of Nature). IUCN Red List of Threatened Species: Ailurus fulgens. Retrieved from: https://www.iucnredlist.org/
- Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute. Red Panda (Ailurus fulgens). Retrieved from: https://nationalzoo.si.edu/animals/red-panda
- World Wildlife Fund (WWF). Red Panda Species Profile. Retrieved from: https://www.worldwildlife.org/species/red-panda